公務員として働きながら、アパート経営などの不動産投資で老後の貯蓄を作りたいと悩んでいませんか。
副業が禁止されている公務員ですが、アパート経営によって副収入を得ることが可能です。
公務員がアパート経営することによって、様々なメリットが得られる一方で、注意したいポイントがいくつかあります。
本記事では、そのようなメリットや注意点について解説していきます。
不動産ライターとして培ったノウハウをここで公開していきたいと思います。
ぜひ参考にして、アパート経営を成功させてください。
スポンサードサーチ
公務員でもアパート経営はできる

副業が禁止されている公務員ですが、アパート経営することは可能です。
アパートを経営するということは、いわゆる不動産投資になるわけですが、不動産投資は副業とはみなされていません。
そのため、公務員でもアパート経営による副業しても問題ないのです。
しかし、ある一定の条件をクリアする必要があります。
そこでここでは、公務員がアパート経営する場合にクリアしなければならない条件について解説していきます。
公務員がアパート経営する際の条件
公務員がアパート経営する際の条件は、大きく3つあります。
- 管理業務を不動産管理会社に委託すること
- 年間収入を500万円以下に抑えること
- 4棟9室以下の規模であること
この条件をクリアしなければ、たとえ副業とみなされない不動産投資であったとしても、減給や免職処分の対象となる可能性があるため注意しましょう。
それぞれについて解説していきます。
管理業務は不動産管理会社に委託する
1つ目の条件は、管理業務は不動産管理会社に委託することです。
アパート経営には、入居者の募集や建物のメンテナンスなど、多くの管理業務が発生します。
公務員として働きながら、このような管理業務を1人で行うことは不可能に近いでしょう。
さらに、公務員には「職務に専念する義務」が課されているため、公務員としての業務以外に集中してしまうと、義務に反する可能性が出てきます。
そのため、管理業務については不動産管理会社に委託する必要があるのです。
年間収入を500万円以下に抑える
2つ目の条件は、年間収入を500万円以下に抑えることです。
アパートを経営していると、住んでいる人から家賃が支払われます。
この家賃がアパート経営している人の収入となるわけですが、家賃収入が年間で500万円以下となるようにしなければなりません。
500万円以下という数字は公務員の副業が禁止されている、人事院規則14‐8(営利企業の役員等との兼業)の運用についてで定められています。
そのため、アパート経営による年間収入を500万円以下になるよう、家賃の設定しましょう。
4棟9室以下の規模であること
3つ目の条件は、経営する物件は4棟9室以下の規模であることです。
こちらも前項と同様に、人事院規則14‐8(営利企業の役員等との兼業)の運用についてで定められています。
例えば、2部屋あるアパートを4棟経営することは問題ありませんが、3部屋あるアパートを4棟経営してはいけません。
人事院規則に抵触することになり、処罰の対象になってしまいます。
そのため、不動産投資する際は、物件の規模を4棟9室以下となるようにしましょう。
所有する不動産が一定規模以上の場合は申請すれば許可してもらえる場合がある
万が一、所有する不動産が一定規模以上の場合でも、申請することで許可が得られる可能性があります。
しかし、基本的には特別な理由がない限りは許可が降りることは少ないでしょう。
特別な理由としては下記のようなことが想定されます。
- 親からの生前贈与や相続によって不動産を所有した場合
- 転勤などで住んでいる自宅に住めなくなり賃貸物件とする場合
このような場合には、物件の規模が4棟9室以上であっても許可が得られる可能性が高いといわれていますが、必ず許可が得られるわけではないので注意しましょう。
公務員は融資が受けやすくて不動産投資が有利

公務員の不動産投資は、民間企業に勤務する者と比較して有利だといわれています。
その理由は、不動産投資する際、金融機関からの融資が受けやすいことにあるのです。
公務員としての立場上、社会的な信用度が高いことは強みになります。
融資する側の金融機関としても、社会的な信用度が低い人に融資するよりも信用度が高い人に融資する方が未回収などのリスクを減らすことが可能です。
このような観点から、他の副業と比較しても不動産投資においては公務員ならではの強みが活かせます。
公務員がアパート経営するメリット
不動産投資において強みを持っている公務員ですが、不動産投資としてアパート経営するメリットが4つあります。
- アパートローンの審査に通りやすい
- 信用度が高く低金利で融資が受けやすい
- 不労所得が受けられ生活の安定感が増す
- 相続税の対策になる
それぞれについて解説していきます。
アパートローンの審査に通りやすい
メリットの1つ目は、アパートローンの審査に通りやすいことです。
公務員という職業は、社会的な信用度が高く、様々なローンを組む際に有利に働きます。
その中には、不動産投資することを目的としたアパートローンも含まれているのです。
自己資金のみで不動産投資ができればベストですが、現実的には資金を調達しなければならないことが多いでしょう。
そのような場合でも、公務員であればアパートローンの審査に通りやすいため、メリットとなるのです。
信用度が高く低金利で融資が受けやすい
メリットの2つ目は、信用度が高いことから低金利で融資が受けやすいことです。
社会的な信用度の高さは、単純にローンの審査に通過しやすいだけではなく、金利にも影響します。
金利が高ければ借りた金額よりもより多くの返済をしなければなりませんが、低金利であれば、その負担額は軽減されるのです。
そのため、アパート経営において低金利で融資が受けやすいことはメリットと言えます。
不労所得が受けられ生活の安定感が増す
メリットの3つ目は、不労所得が受けられ生活の安定感が増すことです。
アパート経営では、基本的な業務はほとんど行うことがなく、入居者からの家賃が収入となります。
家賃収入に加え、公務員としての給料も発生していることから、経済的な余裕を得やすいといえるでしょう。
経済的な余裕が出てくると、生活の安定感も増してくることはメリットになります。
相続税の対策になる
4つ目のメリットは、アパート経営が相続税の対策にもなることです。
相続と聞くと現金を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、現金での相続の場合、評価額が100%になってしまいます。
一方で、アパートや不動産での相続の場合、評価額が2〜3割減となるのです。
さらに、相続税対策としての不動産投資に関しては、公務員の副業に対しての許可が出やすいといわれているので、大きなメリットになります。
アパート経営の注意点
公務員によるアパート経営では、大きなメリットがある一方で、気をつけなければならない注意点があります。
- 懲戒処分を受ける可能性がある
- 確定申告が必要
- 自然災害によるリスク
アパート経営を成功させるには押さえておかなければならないポイントです。
ここでは、それぞれについて解説していきます。
不動産所得を正しく申請しなけば懲戒処分を受ける可能性がある
不動産投資で得た所得を正しく申請しなければ、懲戒処分を受ける可能性があることを理解しておきましょう。
例えば、所得が漏れている場合には脱税となり、法律に反することになってしまいます。
万が一、正しく申請ができなかった場合、減給処分になるだけでなく、懲戒免職のように非常に厳しい処分になることを理解してください。
そうならないためにも、不動産投資で得た所得は正しく申請しましょう。
確定申告は必要になるので忘れない
アパート経営によって発生した利益については、確定申告しなければなりません。
公務員としての給料のみが所得になっている場合は、職場で年末調整することによって確定申告は不要となっています。
しかし、アパート経営による利益は、年末調整に含まれないため自分で確定申告する必要があるのです。
年に1度しか申請するタイミングがないため、必ず忘れないようにしましょう。
自然災害によるリスクはある
アパート経営する際は、自然災害による不動産の倒壊などのリスクについても理解しておきましょう。
日本に住んでいる以上、地震や台風などの自然災害は付きものです。
自然災害に見舞われた際には、倒壊や水害など、様々な被害が考えられます。
このような被害を受ける可能性を少しでも低下させるため、自分が不動産を所有したい地域の自治体が発行しているハザードマップなどを参考にすると良いでしょう。
また、火災や地震保険などに加入しておくのも有効です。
スポンサードサーチ
まとめ

公務員が不動産投資の1つとしてアパート経営するには、一定の条件をクリアする必要があります。
しかし、条件をクリアさえすれば、公務員としての社会的な信用度の高さによる恩恵を存分に受けられます。
もちろん、法律で定められている確定申告などを忘れてはなりません。
このように、メリットも注意点も存在する公務員のアパート経営ですが、老後の貯蓄を作るにはおすすめの副業です。
ぜひ本記事を参考にして、あなたも不動産投資に挑戦してみてください。
処女作『副業公務員~仕事以外で稼ぎたい・辞めたい・独立したい市役所、県庁で働く人へ~』配信中!
有料カテゴリーランキング1位獲得!
公務員時代の副業ノウハウを凝縮
本書は地方公務員(志願者含む)のための副業攻略本です。
市役所・県庁で副業を経験した現役著者/ライターが、あなたの副業ライフを加速させるため、「本業以外で稼ぐ方法〜副業をする時間作り、仕事の手の抜き方から独立後の生活まで網羅した一冊」を書きました。
“バレない副業の仕方”や”定時帰りする仕事術”を知りたい方はご一読ください。


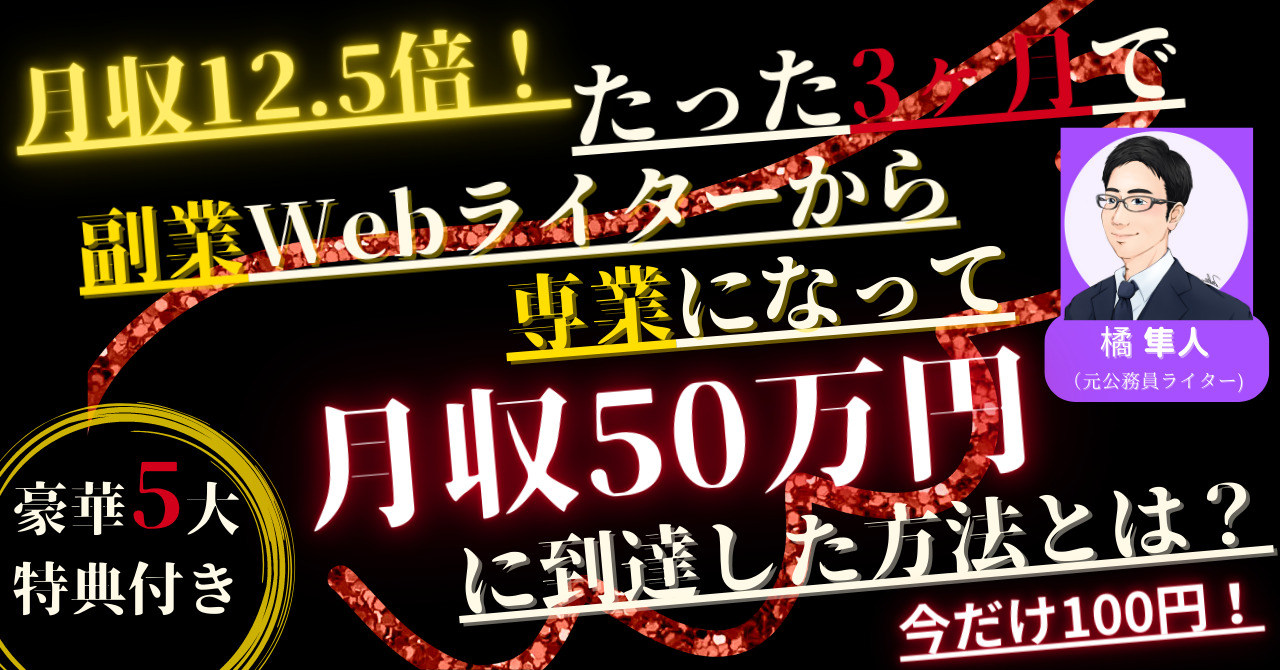
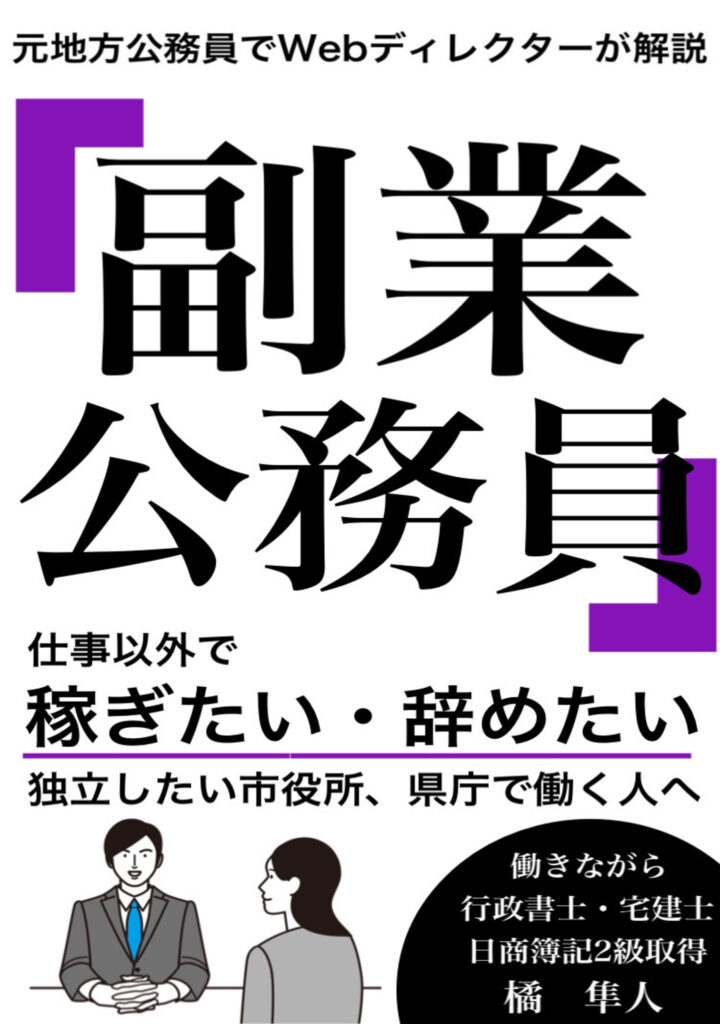







スポンサーリンク